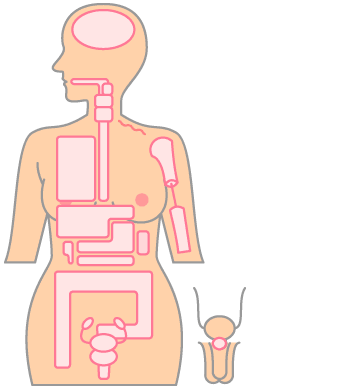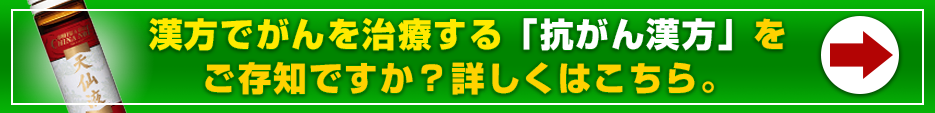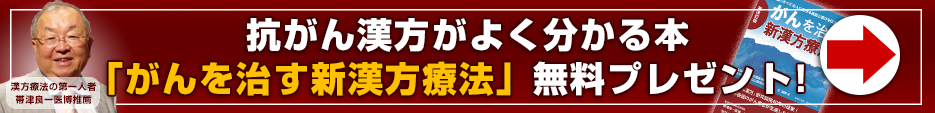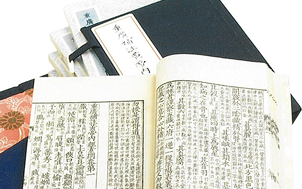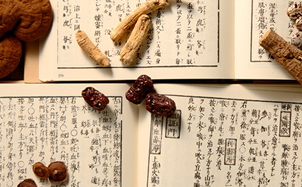骨髄腫
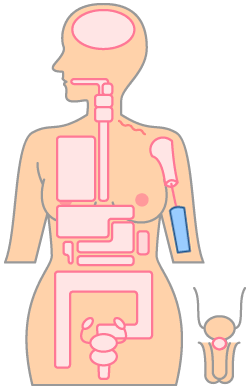
白血球の一種である形質細胞は、外部から侵入した病原体を見分け、抗体を作る働きをしています。多発性骨髄腫は、この形質細胞の突然変異で起こります。血液のガン(肉腫)の一つで、とくに60~80歳代の高齢者に多く見られますが、日本では10万人に数人程度の発症です。
性質の異なる形質細胞が作られると(突然変異)、まれに性質の異なる強力な形質細胞が現れ、骨髄で無制限に増殖することがあります。このような細胞を「骨髄腫細胞」といい、これによって起こるのが、多発性骨髄腫です。発症すると骨髄腫細胞が増殖し、全身の臓器にさまざまな障害が起こります。
骨髄腫細胞には骨を溶かす特徴があり、いろいろな骨が破壊され、骨折を起こしやすく、それがきっかけとなって発見されることもあるようです。
骨髄腫の症状
- 造血障害
- 骨髄腫細胞が異常に増えることにより、正常な造血が妨げられ、赤血球や白血球、血小板の数が少なくなります。そのため、貧血や抵抗力の低下が起こり、感染や出血しやすくなります。
- 腎機能障害
- Mたんぱく(細胞や組織に付着する、抗体に似た成分)が「糸球体」に付着し、老廃物を体外に出すことができなくなります。
- 骨折や神経障害
- 破骨細胞が増加して、骨からカルシウムが過剰に溶け出します。突然骨が折れたり、骨髄細胞の塊が骨の外に飛び出し、神経を圧迫し、激しい痛みや手足の麻痺が起こります。
- 多臓器不全
- Mたんぱくの破片が溜まり、関節のこわばりや味覚障害、不整脈を起こすことがあります。
- 視力障害
- 赤血球同士がつながってしまい、網膜など細い血管の血流を妨げて視力障害を起こすことがあります。
- 意識障害
- 骨が溶け出すことにより、カルシウムが血液中に過剰に流れ出すと、カルシウム濃度が上昇し(高カルシウム血症)、意識障害が起こることがあります。また、血液中のアンモニアが増加する「高アンモニア血症」が起こり、意識障害に至ることがあります。
骨髄腫の発見方法
血液中のMたんぱくを調べる方法が有効ですが、特殊な検査であるため、尿検査や血液検査で総たんぱく量の変化を調べたり、骨のX線検査が行われます。多発性骨髄腫が疑われる場合は、骨髄穿刺(骨髄に針を刺して形質細胞を採取)を行います。
骨髄腫の治療法
MP療法(化学療法)
メルファラン(抗ガン剤)とプレドニゾロン(副腎皮質ホルモン剤)を併用する両方がよく行われていますが、メルファランなどのアルキ化剤を長期間使用すると「自家抹消血幹細胞移植」が困難になるため、一般的には移植ができない場合に行われます。
インターフェロン(抗ウイルス作用があり、C型肝炎治療に用いられる)、放射線療法(病巣が狭い場合などに有効)、造血幹細胞移植、骨吸収抑制薬(骨を溶かしてしまう破骨細胞の働きを抑える)、サリドマイド(多発性骨髄腫に有効とされる海外の報告あり)。
様々ながんについて学ぶ
知りたいがんの種類を選択してください。